マネジメント方法は業種や職種で違いはあるのか?【元リクルート役員が解説!】
- yoshihisa togashi
- 2025年7月20日
- 読了時間: 11分

マネジメント総数10,000人以上!元リクルート役員で弊社、株式会社エクスペリエンサー取締役 冨塚 優(通称:トミー)が主催する、人材育成、組織開発のナレッジが詰まったYOUTUBEチャンネル「ポケカルビジネスTV」の内容をダイジェスト版としてご紹介していきます。
弊社の組織人事に関わる課題解決サービスについては、こちらより
【この記事(マネジメント方法は業種や職種で違いはあるのか?)で書かれていること】
マネジメント方法は業種や職種で違いはあるのか?
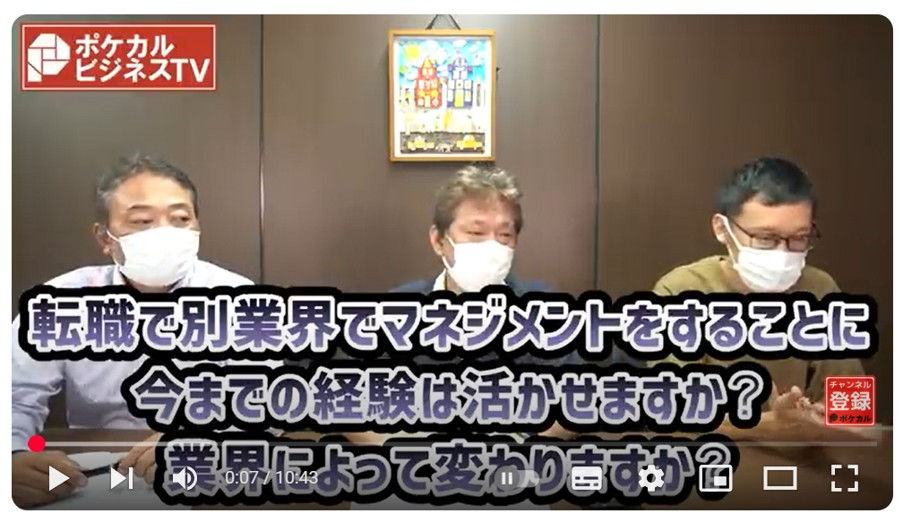
(ヒガキ)はい、よろしくお願いします。
(トミヅカ、ハラダ)よろしくお願いします。
(ヒガキ)本日もですね、視聴者からの質問になります。今までIT企業でマネジメントしていたんですけれども、今回転職を機にですね、飲食業界のマネジメントをすることになりますので、今まで通りのITとかで培ってきたマネジメントで、飲食業界でも同じことをやっていっていいのか。マネジメント方法は業種や職種で違いはあるのか?っていうちょっと難しい質問をいただいております。
(ハラダ)変わらないんじゃないの?変わらない部分と、変わる部分があると思うけど、根本は変わらないんじゃないの?だってマネージメントって何だっけみたいな話って前に一回やってたと思うけど、結局は伴走していくっていうところなんだから、そこは変わらないじゃん。

(ハラダ)だから別に業種によって変わらないけど、それぞれの業界や仕事や、経理は経理で大切にしてることって、数字の確実性とか、納期とかだし。営業でいえば、数字を上げることだしとか。ゴールが違ったりとか、求めているものの何かが違う部分があっても、結果的には、それをマネジメントするっていうか、それを部下ができるようにしてあげる環境を作るとか、変わらない気がするけど。
(ヒガキ)業績マネジメント的なところは、そのゴールによって変わるけど、人的マネジメントとかは⋯
(ハラダ)業種や仕事によって、大切なこと変わるから、編集作業と営業とは、似てる部分。根本は結果的に同じだけど、やっぱり違うところもあるから、そこは違うけど、変わらない気がするんだよな。どうなんだろう。
原理原則は一緒。各論は違う。
(トミー)もうちょっと違う言い方をすればね、原理原則は一緒ですよ。原理原則は一緒。だからやりくり上手になってねとか、ちゃんと伴走してねとか。原理原則は一緒なんだけど、例えば、相撲取りって、相撲でどうやったら勝てるんですかって話と、水泳でバタフライでどうやって勝てるんですかっていうのと、マラソンでどうやったら勝てるんですか、ジャンプでどうやったら勝てるんですか、それはトレーニング的には、同じかもしれないけど、その中で勝つって言ったら、そういう勝ち方とか、どういう風にすれば勝てるのかっていうのは、その競技なりのものってのはあるよねって言ってるのと同じような気をしますよっていう。
(ハラダ)そうですよね。

(トミー)そういうことだと思うけどね。だから、「同じですか?違いますか?」って言ったら、根本は同じだけど、各論は全く違いますっていう風に。そりゃそうだよ。だって例えばいくつかあって、まず慣習が違う。習慣が違うと慣習が違うっていうことがあるんで。
例えばIT業界で、まあITって言っても広いから、色々あるかもしれないけれども、そのITに勤めてる人のITリテラシーと飲食業のITリテラシーって同じですかって言ったら違うの。となったら入ってるツールも、使ってるツールも違えば、それに対してのマネジメント方法も違うでしょうと。それを「このツールを入れてこうでこういう風にやれば、合理的にできますから、これでやりましょう」って言っても、「いや、そんなもんないし、まずそれをメンバーに理解させるのが大変だから、そういうことではないやり方でやってくれよ」って言われたら、これやり方が違うよねっていう話もなるわけだし。

(トミー)例えば正社員の比率とアルバイトの比率っていうのも全然違うかもしれないよねと。IT業界の場合には、もうほとんどの人が正社員だって話だけど、飲食業界へ行くと逆に社員が少数で、ほとんどがアルバイトですとか。こちらは大学卒ですごく理工系で学んできた人多いけれども、こっちは別に学校なんて関係ないよというようなところで、いかにちゃんとした接客ができるかってことの方が大事だっていう風になってれば、それはコミュニケーションの取り方も変わってくるから、コミュニケーションのスタイルが変わるということは、マネジメントのスタイルが変わるってことですから。それは全然違うと思いますよ。
もうちょっとこう突っ込んでこういうこと言うとどうかと思われるかもしれないけど、例えば、まあSPIみたいな取ってね、能力の点数が言語と非言語で何点ですみたいなものがあって、そもそも例えば7点の人の集団と、2点の人の集団。マネジメント同じにするかって言ったら、それは違うよねって分かりやすくどうやって伝えるんですかっていう。
原理原則、分かりやすく伝えるっていうのは一緒だけど。
(ハラダ)そうですね。

(トミー)各論に直したら、かなり違いは出てくると思う。
(ハラダ)そこを聞いてらっしゃるんでしょうね。
(トミー)いや、そういうことじゃないですか。
(ハラダ)今思いましたけど、IT業界なんて今普通に多分リアルというよりも、リモートで会議したりとか、Zoomが当たり前と思うんですけど、飲食業界だとリアルが基本じゃないですか。全然文化の違いは、そのコミュニケーションスタイルも違うから、それはそっちに合わすしかないですよね。
(トミー)まあ合わせると言うか、それを前提として、どういう風にコミュニケーション取っていくんですかっていう話だから。
(ハラダ)そうですよね。そういう意味では、郷に入れば郷に従え。前提にするっていう風に思わないと無理だわ。その根本のことは変わらないけど、確かに⋯
(トミー)だから原理原則は一緒なんですよ。
(ハラダ)はい。
業界に限らず会社によっても大切にしていることは違う
(トミー)一緒だけど、やり方とか伝え方とか、同じ飲食業界でも会社によって全然違ったりするでしょ?例えば、吉野家さんとゼンショーさんは一緒ですか?いや、同じところあるかもしれないけど、違うところもあるかもしれない。
(ハラダ)そうですね。全然大切にしているものが違いますもんね。

(トミー)それは昔僕らは求人の仕事をやっている時に、企業を見るメガネっていう研修を受けましたけど、例えば、紳士服の青山商事とAOKIは、何が一緒で何が違うのかみたいなものって、まず理念が全然違うし、企業としての成り立ちが違うから、経営者が大切にしてることも違うし、そこから企業の理念とか、文化っていうのが出来てるから、同じ紳士服を取り扱ってても全然思想とやり方が違うんですよ。やり方が違えば、マネージメントの仕方も違うっていう。
(ハラダ)そうですよね。
(トミー)ただし、言っているように、原理原則は一緒だっていうね。
(ハラダ)評価も変わりますもんね。それによってね。そう、その話は本当は深堀るとすごい面白いんだけど、CannonとNikonの違いとかもあるし。
(トミー)だから、何を大切にしているのかっていうのは企業文化によって違って、とにかく売上が大切ですっていう企業もあれば、顧客満足が大事なんだという会社もあるわけですよ。例えば何かトラブルが起こった時に、それは「半額ぐらいの返金でいいだろう」みたいなことで、合理的な判断。

(トミー)なぜならば、これだけかかって、これだけかかって、こうで実際にこういうようなことが実行されてるわけだから、「これぐらいが合理的だよね」っていうのもあれば、「お客様は満足はされてないんだから、結局今後のリピートとかもね、考えたり、評判っていうのを考えたら、もう全額を負担するのも当たり前じゃないか」っていう風に考える会社もあるわけですよ。それは思想が違うわけで、どっちが良いとか悪いとか、正しいとか正しくないじゃないんですよ。それはもう自分に合うか、合わないかって話だけど。
その中でマネジメントしていくっていう話になると、「何を大切にしてるから、こういうやり方をしていくべきだよね」っていう風に本人が思って行動をしていくってことでしょ。だから、そこがずれてると、もう「全く違うよね」って話になると思う。

(ヒガキ)自分がやったことのない部署の管理職になるみたいな話を動画で撮らせてもらった時に、すぐに目に付いたものを改善しようみたいな話があって、じっくりちゃんと見極める期間を取ったほうが良いっておっしゃってたのも、その文化とか、そういったものをちゃんと自分で把握しましょうっていう時間になるってことですかね?
(トミー)そういうことじゃないですか。例えば、こうやってマネジメントの話をいっぱいして、色々なお便りね、メールをいただくわけですけど、結構多いのが、看護系の仕事に就いてる方から来るケース多いんじゃないですか。そうなるとやっぱ看護業界っていう業界を理解した上で、「うちの業界とはちょっと全然違うから、この話、合いませんよ」っていう風に言ってくる人もいれば、「トミーさんがやってたリクルートのマネジメントと看護業界は違うんだけど、でもその原理原則のところっていうのを理解していただくと、業界が違っても、共通でこれを応用して使えるところがすごくあって参考になってます」っていう、両方来るじゃないですか。
業界が違っても応用できることはある
ここがやっぱり大事だと思ってて、応用できるかどうかっていうことですよ。昔ね、研修商品を販売してる時に、人事OKで、現場の人に研修をやってる時に、僕はオブザーブで一緒にいてね、見てて、で、アンケート見ると、「事例が違う業界の内容になってたから、全く役に立たなかった」みたいにつけてる人がいるんだよ。で、これを見た瞬間に、「こういうレベルの人たちなんだな」ってやっぱ思うわけですよ。

(トミー)そこは咀嚼して、原理原則の勉強してるわけだから、業界が違っても重箱の隅をつつくように、「うちの業界はそうじゃないんです」っていうんじゃなくて、それはそういう風に捉えて、「自分がもしその業界にいたとして」っていう風に仮置きをした上で、でそれに対して、こういう感じの打ち手を打ってくんだなっていうのを学ぶ。
学んだら今度、自分の会社に置き換えた時に、その学んだことはどうやって活かして良いのかっていうことを考えて実行ができる人、こっちはやっぱり優秀なマネージャーになっていく人なんですよね。
だから今回のお話で言えば、「違うんですか?」って言ったら、「違います」。ただ原理原則は一緒だから、そこをその現状の飲食業界に当てはめて考えたら、どういう風にしていけば良いのかっていう。前のITの時にやってた、これでやって成功したから、じゃあこっちで同じことやって成功するかっていったら、相手が違うから、それは成功しないですよという風に思いますよ。
(ヒガキ)ありがとうございます。

(トミー)もう1個重要なことが、「原理原則」とは何かってことをちゃんと学ぶってことですよ。マネジメントの原理原則。分かりますか、マネジメントの原理原則?
(ハラダ)原理原則。どうぞ!
(ヒガキ)やりくり。
(ハラダ)やりくり上手?
(トミー)ハラダくんはさっき、伴走するっていう風に言ってましたけど、原理原則ってのいくつかあるんで、これはものの本を読めば、マネジメントの原理原則っていうことは書いてありますから、そういうことぐらいは、ちゃんと学習をするっていうことが必要だと思います。
(ハラダ)うちの動画の中にも「マネジメントとは?」っていうのがあるので。見てもらうっていうのが良いと思うんですよね。
(ヒガキ)はい。原理原則を勉強しながら、各論にマッチするように、カスタムしていければと。

(ハラダ)そうですね。やっぱ想像力が必要だなと思いますよね。違うとこに入ってた時に、そこは何が大切なのかとか考える想像力とか。それでも自分がやってきたことの中で、これが活かせるよって思うこととか。
(ヒガキ)僕、型はめ型なので、そのマッチ型を頑張って目指したいと思います。
(ハラダ)あーーなるほどね。
(ヒガキ)はい。本日もありがとうございました。
(ハラダ)はい。どうもありがとうございます。
●実際の動画はこちら
ポケカルビジネスTV YOUTUBEチャンネルはこちら
●人材育成・組織課題の解決支援を行う株式会社エクスペリエンサーは元リクルート役員冨塚と、同じくリクルート出身の富樫とで共同創業をした会社です。
人材育成は体験に軸足を置いた研修が特長。組織課題の解決は、各企業のありたい姿の実現に寄り添い、現状とのGAPを埋める課題解決策の実行を支援いたします。何かしらの人と組織にまつわる課題の解決をお考えの企業様は、是非お気軽にお問合せください。






