プレイングとマネジメントを使い分けるためのOODAループとは?【元リクルート役員が伝授!】
- yoshihisa togashi
- 2025年8月10日
- 読了時間: 11分
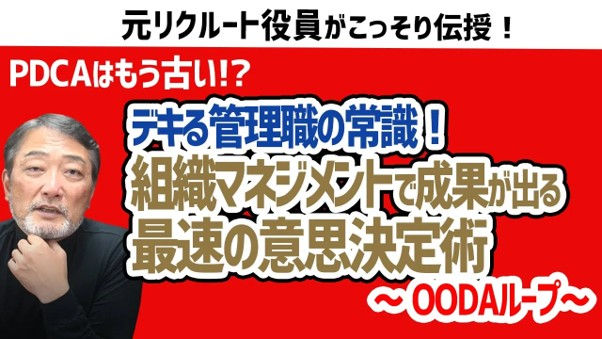
マネジメント総数10,000人以上!元リクルート役員で弊社、株式会社エクスペリエンサー取締役 冨塚 優(通称:トミー)が主催する、人材育成、組織開発のナレッジが詰まったYOUTUBEチャンネル「ポケカルビジネスTV」の内容をダイジェスト版としてご紹介していきます。
弊社の組織人事に関わる課題解決サービスについては、こちらより
【この記事(プレイングとマネジメントを使い分けるためのOODAループとは?)で書かれていること】
プレイングとマネジメントが上手く回っていない

(ヒガキ)はい、よろしくお願いします。
(トミー、ハラダ)はい、よろしくお願いします。
(ヒガキ)今日はですね、マネージャーとして、プレイングの配分とマネージメントの配分っていうところが、ちょっとうまく回ってないなっていう風に思っておりまして、どういう風にやれば、こうマネジメントの業務をきちんと回せるかというところをお伺いしたいっていう風に思ってます。
(トミー)はい。
(ヒガキ)特に今新しい事業とかやってると、結構自分でガーッと回しちゃってることが多くて、で、それをこうメンバーに任せようっていった時に、整理が自分でもできてない時とかがあると、いつまで経っても忙しいし、メンバーにその業務を託せないっていう悩みがありまして。
(ハラダ)ちなみにそれは、託そうと思えば託せるのに託してないの?それともいないからしょうがなく自分でやってるの?どっちなの?それによって全然意味が違うと思うんだけど⋯
(ヒガキ)どちらかというと⋯説明とかが面倒くさいっていう方に近いですね。
(ハラダ)ってことは、例えば今やる人がいなくて自分しかいないから、やってるとかっていうわけでもない?
(ヒガキ)いや、ないです。はい。
組織目的に向けて自分と配下メンバーの役割を設計する

(トミー)その話で言えば、もうずばり今日は回答は1つしかなくてですね、この件に関して言うと。前々からこのYouTubeで私は申し上げてますが、組織というのは、組織目的がある訳ですよね。で、この半期なり、このクォーター(四半期の意味。3か月)なり、この1年なり、この組織がどういう状態になって欲しいのか、ゴールっていうのはある訳ですよ。で、それに対して、現状は届いてない訳だから、そのゴールに向かって組織で活動していくという話なんですよね。
で、その組織の活動の成果を責任を持っているのが、そこの組織長。ですから、マネージャー、今日のところで言うのであれば、だからヒガキ君に対して、私はポケットカルチャー社として、あなたの組織にはこういうことをやってほしいですと。で、こういう状態にしてほしいよというミッションをお願いしてる訳で、それをヒガキ一人でできるんだったら、やってもらえばいいんだけど。
とてもじゃないけど、一人じゃ無理だよねと。だからメンバー付けますよとっていう風にお願いしてる訳です。で、それを我が事として受けた時に、自分は何をして、配下の4人のメンバー誰には何をしてもらうっていう、この計画ができていないと、まず話になりませんよねということなんですよ。
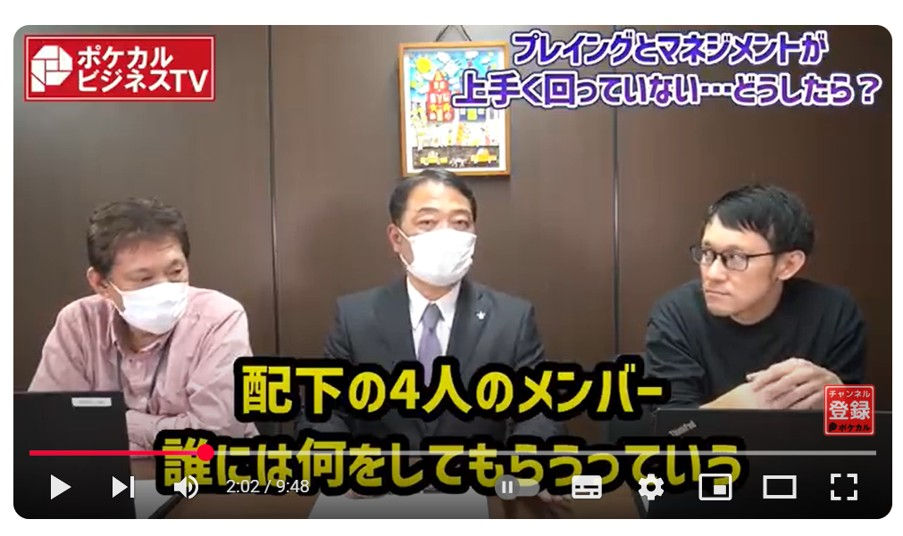
(トミー)で、自分が手を動かす部分っていうのは、自分が手を動かしてやる部分だし。配下のその4人の人にお願いした部分に関しては、これがちゃんと計画通りに進んでいるのかっていうことをチェックをしていく。で、彼・彼女の指標とミッションがしっかりと遂行できるように、アドバイスをしていくっていうのが役割ですよね。なので、それがミッションとして、仕事の中身として、どういう項目だってことを挙げると同時に、もし可能であれば、時間の配分もそうで、自分のスケジュールというものが1日例えば9時⇒17時とするんであれば、9時から17時の間の時間に何の時間にどれだけ使うのかっていうことを、1日もそうだし、大体まあ1週間の人が多いと思いますけど、1週間でそれを計画すると。
プレイヤーとしてやるべき業務の時間は週36時間のうち何時間ねとかねっていうのはやっぱり決めるんじゃない。で、それに対してそれが、自分が思うように進んでないのか、進んでいるのか?メンバーのAさん、Bさん、Cさん、Dさんというこの4人が、予定に対してどういうような進捗具合になってるのか、場合によっては巻き取らなきゃいけない時もあるから、自分が手を動かさなきゃいけない時もあるんだけど、このプランニングがちゃんと出来ていないと全く話にならないし、そのプランに対して現状はどうなのかっていうのをPDCAを回すというようなことをしていれば、プレイングのボリュームとマネジメントのボリュームが、ああだこうだってことを、悩むようにはならないと思いますよ。
新しい業務で業務量が読み切れない場合はどうすればよいか?

(ヒガキ)今お話をお伺いして、自分なりに思ったことが1個あるんですけど、新しいことやってる時って、この業務量の読みっていうのが結構間違えちゃって、で、自分ではこれぐらいで終わるんで、ちょっと設計して渡せるようにできるかな、解りやすくできるかなっていう時に、想像以上に膨らんでしまった結果、渡すタイミングが週送りになっていくっていうのが結構多いですね、今は⋯
(ハラダ)結局、渡したらできないんじゃないかってこと?
(ヒガキ)いや、理解ができる形にできてないです。自分の中の資料とかっていうのが作れてないので、とりあえずもう自分で、ぶん回しながら、今日も疲れたみたいで終わって⋯
(ハラダ)渡そうっていうことは考えているの?
(ヒガキ)それは考えてます!はい。それが結構多いですね⋯
(ハラダ)逆に言えば、いつまでだったらできるっていうのは自分の中では考えてるの?やってる中で、分量見えてくる訳じゃん。
(ヒガキ)そうですね。今週この時間にそれを作るっていう風に充てようと思ってたら、ちょっと違うトラブルとか、読み違えてて、自分でやらなきゃいけないことの作業が多くなって、考えるとか、設計するとか、資料を作るとかっていう時間が後回しになっていくっていう⋯
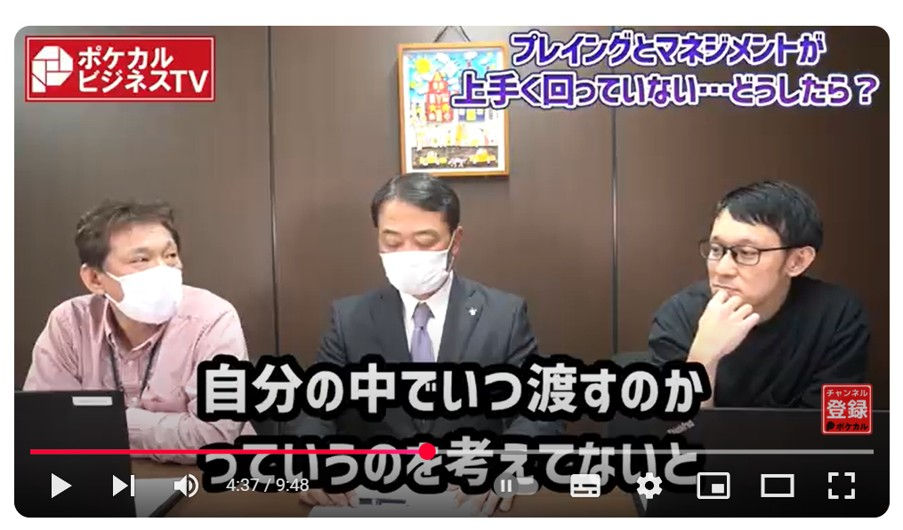
(ハラダ)ちゃんとそうは言っても、自分の中でいつ渡すのかっていうのを考えてないと、いつまで経っても渡せないよそれ、多分。
(ヒガキ)そうっすね⋯
(ハラダ)と思うけどな。やっぱりちゃんと任せなきゃいけないのは、任せなきゃいけないし。じゃあ、何やればいいの?ってなっちゃうし、下の人は。いなくて自分だけでやるんだったら、別だけど。
(ヒガキ)そこはちょっと難しい。うまく回ってないなと思う時が結構あります。
(トミー)でもそれはよくあるよね。やっぱり初めてのことだから、経験値もないから、自分はこれぐらいでいくんじゃないかなと思ったけど全然いかなくて、自分のワークがものすごくオーバーフローをしてしまうっていうようなことっていうのは、よくあることだと思いますよ、現実的には。ルーティンの仕事を回している人は、そういうことないですけども、で、そういう時にはね、さっきから、僕はPDCAを回すって言い方したけど、今の世の中で合わせて言うんであれば、まあPDCAというよりは、OODAの考え方かなと思う訳ですよ。
プレイングとマネジメントを使い分けるためのOODAループとは?

(トミー)いわゆるオブザーブですね、観察をする、だから現状どうなってるのかっていうのを観察をすると。で、オリエントで適応する。で、その次がディサイド。
(ハラダ)あ、ディサイド。
(トミー)ディサイド分かりますか?
(ヒガキ)決断する。
(トミー)決断する。で、何をするかっての決めて、で、アクション。
(ハラダ)アクション。
(トミー)またそれをアクションをオブザーブするっていうね。計画してるなんていう暇があれば、もうどんどんどんどん回していって、で、それを見ながら修正をして、情報共有しながらねっていうOODAっていう考え方が、これも軍事用語ですけれども、ありますが。そういうようなことで、どんどん修正していくしかないですね。計画というよりは、とにかく実行しようよと、で、してみてそれを見ていて、これは、それは、うまくいかないなあ。であれば、こういう風に変えようってことを意思決定をして、またみんなで一緒にそれをやるみたいなというようなことを、どんどんくるくるくるくる回していくんだと思いますよ。こっちの方がまあ早いし、未知の仕事をやる時には。
それをね、前職リクルートさんの時には、朝礼朝改って言ったんすけど。
(ヒガキ)ああ、なるほど。
朝礼朝改をすべき時もある

(トミー)朝令暮改っていうのは、朝決めたことがなぜかもう夕方には違うっていう風に言われてるっていう、リクルートの中ではよく、朝礼朝改って、朝決めたことをもう朝変えるみたいなっていうのは、やっぱりOODAの考え方の方が適しているっていう、そういう感じでしょうね。
ちょっとうまくいかないと思ったら、すぐ変えるっていう、というようなことだと思います。なので、それは言ってることもよく分かるんで、どんどんどんどん早く動いていくっていうことが必要なんだと思いますよ。
(ヒガキ)分かりました。多分メンバーへの指示とか、お願いすることっていうのが、変わっていくと、彼らが混乱するんで、まずしっかりした方針を決めたいっていうのが多分強かったんです。

(トミー)それはね、方針はちゃんと決めないとダメですよ。一番最初にちゃんとした方針を決めるんです。でも決めるけど、やったことがないことだから、どういう形になってるのか分かんないんで、それはウォッチしながらどんどんどんどん変化をさせていくっていうコンセンサスを取っておくということが重要です。
(ハラダ)そこはコンセンサスが大切だね。そこを巻き込みながらやっていくっていうのは大切。計画が出来てないから、自分だけでやるっていう風にしちゃうと、一番悪いから。
(ヒガキ)そうですね。
(トミー)ただそのOODAは、要は戦争が実際に起こってる時に、それを遠隔にいる指令本部はいちいち指示出せない訳ですよ。いきなり目の前に、なんか降ってきましたっていう時に、今からそれに対して計画立てるからなんて言ってるうちにやられちゃうっていう話でしょ。
なので、もうその状況判断をしながら、意思決定をして、で、それを見ながら、次の手どうするかっていうのを素早く変えていくっていう、そういう軍事用語から出てきてる訳ですけど。だから、ビジネス的にも、最初はプランは立てないとダメですよ。で、それがうまくいかないなってなったら、何でうまくいかないんだろうっていうので、ここを修正してこういう風にやろうかっていう。
元の質問に戻しますけど、結局プレーヤーの部分とマネジメントの部分っていう風に言ってるんだけど、優先順位がどちらが高いんですか?って話です。どっちですか?
組織目標を達成するための道筋をメンバーと共有することも重要

(ヒガキ)組織目標によるんじゃないですか⋯
(トミー)その通りですね。
(ハラダ)なるほど。
(トミー)今日はヒガキくんが良いことを!組織目的を達成するには、どちらをどういう風に優先していく?だから問題なのは、それはちゃんとメンバーとシェアすることですね。
(ハラダ)そう、そう、そこ、そこだと思うよ。
(トミー)そこがないと、「なんか言ってること違うじゃん」っていう風になっていくっていう。そんなようなことでしょうかね。
(ヒガキ)計画の大事さは理解したんですけど、そこら辺の自分がこう⋯
(ハラダ)面倒くさいと思ってるだけじゃないの?~
(ヒガキ)いや、うまくできない⋯
(トミー)でもね、これは違う時に言ったけど、いわゆるその、大課長と部長の違いっていうのは、要は、人にお願いしながら仕事がどれだけできるかっていうことによって、お願いしながら大きな仕事をやっていく人は、部長になれるけど、なかなか人にお願いしきれない。自分でやった方が早いとか、説明するのがもう大変だから、自分でやっちゃうみたいな人っていうのは、大課長にしかなれませんっていう。

(ハラダ)さっき一番最初に説明するのが⋯って自分ですよね。
(ヒガキ)まさにおっしゃる通りだと思いますね⋯今回のプレイングとマネジメントを使い分けるためのOODAループとは?で学んだことを肝に銘じます⋯
(一同)本日もありがとうございました!
●実際の動画はこちら
ルビジネスTV YOUTUBEチャンネルはこちら
●人材育成・組織課題の解決支援を行う株式会社エクスペリエンサーは元リクルート役員冨塚と、同じくリクルート出身の富樫とで共同創業をした会社です。
人材育成は体験に軸足を置いた研修が特長。組織課題の解決は、各企業のありたい姿の実現に寄り添い、現状とのGAPを埋める課題解決策の実行を支援いたします。何かしらの人と組織にまつわる課題の解決をお考えの企業様は、是非お気軽にお問合せください。






